今、「システムシンキング」という思考法が注目されています。
複雑化する現代において、何か一つの事象や仕組みにばかり気をとられると、
偏った認識で全体を把握できないまま物事が進み、
間違った解決法で誤った結果に至ってしまったり、
いつまでも成果にたどり着かないまま組織が疲弊していく、
などということもしばしばです。
そのような「木を見て森を見ず」という状態ではなく俯瞰的な視点で
物事を捉えるリーダーに必要な思考法の一つが
この「システムシンキング」です。
最近は、自社の昇進昇格試験に用いる企業も増えてきました。
例えば、「残業時間が多い」という組織の課題に対して、
「アルバイトを一人採用する」という解決法を選んだとしましょう。
ところが、アルバイトが仕事に加わっても、一向に従来のメンバーの
残業は減らない。
そこで、改めて現状把握してみると、
「業務分担があいまいで無駄な作業が多い」
「チームワークが悪く連携ができていない」
「チームの目標が見えず、方向性がバラバラ」
といった現状が見えてきて、
各々の状態を解決するための手段をとった結果、
そのチームの残業時間が減り、一人採用したことでより組織のパフォーマンスが
上がった、という結論に至る場合もあります。
私たちの目に見えるのは、組織の問題の氷山の一角でしかありません。
また、私たちは「”見たこと”を感じ、考える」のではなく、
「”感じたこと”を見て、考える」というように
主観で捉えていることもあります。
複雑系の世の中を正しく進み、成長し続ける組織を創るために、
この「システムシンキング」という思考法は、
リーダーこそ身に付けるべきものです。
★㈲人事・労務では、この「システムシンキング」に関する講義も
取り入れた「課題抽出演習」をリーダー向けに実施しています。
詳しくは、
http://www.jinji-roumu.com/inbp_new2.html
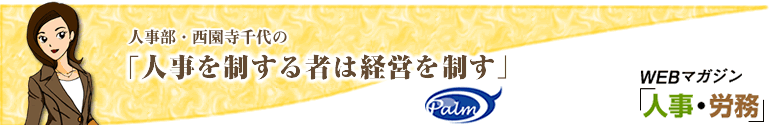
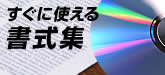
コメント
コメントを送ってください